今回は、難しい連符や吹きにくい箇所がある場合の練習方法をお伝えします。
上手な人や本番で完璧に吹ける人は、みんな効率的な練習をやっています。
今回は私が実際にやっている練習法とプロの色々な先生から教えていただいた練習法をまとめていきます。
それでは見ていきましょう。
まず、難しさの原因を見つける
難しい、上手く吹けない箇所は、なにかしらの原因があります。
まずは原因を見つけましょう。
原因を見つけるために、とてもゆっくりと吹いて観察してみます。私は♩=60以下に落として観察します。
☆Check Point
| ・音の移り変わりの際に、指が無駄な動きをしていないか
・音が変わる時に息の抵抗感はどう変わるか ・正確に自分の思い通りに、指・息・体が動かせているか ・どの音の移り変わりが吹きにくいのか |
などなど、すごくゆっくりに吹くことで観察する余裕が出てきます。
ほとんどの場合、根本的な指や息の使い方に問題があるので、そこを改善すれば吹けるようになります。
ひとつ例えを出すなら、
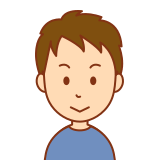
左手の薬指を動かすタイミングが遅いな…早めに動かしてみよう
このように考えながら練習します。
意識するだけで、吹けるようになることもあります!
このように原因と改善法を考えながら練習することで、自分の悪い癖や苦手なポイントがわかってきます。
そうすれば、だんだんと少ない練習でコツを掴んだ効率的な練習ができるようになってきます!
最初は大変かもしれませんが、必ず大きな力になるのでぜひ頑張ってみてください。
連符のおすすめ練習法
ここではひとつ具体的に曲を使ってみていきましょう。
 |
| モーツァルト作曲 クラリネット五重奏 第一楽章 |
青枠で囲まれた、16分音符の連符を練習してみましょう。
連符の音型を理解する
まずは連符の中のまとまりを確認します。
まとまりを探すと、脳が音符を認識しやすくなり指が動かしやすくなるんです。
この譜面だとスラーで4つに分けられていますね。こういう場合はわかりやすいです。
| 1.ファラファレ 2.シレシソ 3.ファソファレ 4.シレシソ
「4つのまとまりがあるな」と認識してください。 |
まとまりを認識できたら、そのまとまりの中身がどの様な音型かを見てみます。
この曲の場合は、4つのまとまりすべて同じような音型です。
| ・1番目と3番目の音が同じ
・2番目で音が上がり、4番目は下がる ・「ヘの字」のような音型 ・分散和音になっている |
これで脳が連符の内容を認識しました。何も考えずに吹くのとでは大きな違いです。
※今回はまとまりを探してから音型を見ていきましたが、この作業は逆でもいいです。
どんな音型かを見て、どこまでがひとまとまりかを探すほうが実際は多いかもしれません。
指を動かすための効果的な練習法
まずは指のための練習法を3つ、楽譜付きで紹介します。

音を1つづつ増やしていき音の流れを理解する方法です。
楽譜には休符をいれましたが、なくても大丈夫です。

そして、2音間の指の練習です。
それぞれの音の間を問題なく吹ければ、通して吹けるはずという考えです。
16分音符でなくても6連符や32分音符など、自分に合わせて変えてみてください。
3番目は定番の練習法、リズム替えの練習です。
指の動きを頭で理解して、譜面のリズムどおりに吹きましょう。
注意するポイント
難しい連符はつい速いテンポで吹いて、吹けた気になってしまうことが多いです。
まずは、ゆっくりのテンポで練習してみます。自分の音をよく聴いて音がちゃんとなっているか確認しながら吹きましょう。
ゆっくりの練習はめんどくさいかもしれませんが、確実に吹けるようになります。
☆Challenge
ゆっくりの練習は基本ですが、爆速で吹く練習もやりましょう。爆速で正確にです。本来のテンポよりも1.5倍ほどで吹きます。
正確に指の動きを認識できていれば、かなり速くても吹けるはずです。
挑戦してみましょう!
指の動きにも注意してください。バタバタと大きく動かさなくても音は変わります。
最小限度の必要な動きを考えながら練習すると効果的です。
具体的に多くの人は、小指や薬指の移動の時に無駄な動きをしていることが多いです。
この曲であれば、ファラの時に左薬指と右人差し指を同時に動かすところが難しいですね。
ファラファラファラファラと速く繰り返してみて、最低限必要な動きを確認しましょう。
音量はいちどフォルテでたっぷり吹くことをおすすめします。音の鳴らし方、つなげ方、息の方向などがよくわかるのでそれを理解してから練習しましょう。
楽器をつかわない練習
楽器を使わない練習法があります。それは、イメージトレーニングです。
「そんなの必要なの?」と思うかもしれませんが、これをやっていると身体の動きの正確さが上がります。
これは、アスリートのメンタルトレーニング法から知ったことです。
運動の分野でのメンタルトレーニングの研究は進んでいます。音楽界でも取り入れる動きは近年海外で出てきています。
日本ではあまり浸透していませんが、数字で結果が出ているので効果は間違いないです。
これは、クラリネットにある程度慣れていないと出来ません。初心者の方は慣れてきたら、自分の練習に取り入れてみてくださいね。
頭の中のクラリネットで吹く
頭の中にクラリネットってありますか?もうすでにある人はとても良いですね!
頭の中での具体的なイメージは、現実での動きをとても助けてくれます。
※指の動き方や、キーの感触、息の抵抗感、音色・・・・かなり具体的に想像してください。
この感覚を掴むためには、それなりにクラリネットを吹いていないと難しいかもしれません。
私もいつのまにか頭の中で吹いていました。
特に、指のイメージは連符の成功率や練習時間の短縮に役立ちます。
スケール練習も、頭の中でやるといいですよ。
まとめ
・上手くいかない原因を探す
・連符のなかのまとまりを理解する
・音型がどうなっているか理解する
・指のための様々な練習方法
・ゆっくりなテンポで音を聴く
・爆速で吹いてみる
・指の動きに注意、動かしすぎや無駄な動き
・頭の中で具体的なイメージトレーニング
効率的な練習をすれば、早く正確に吹けるようになります。ぜひ試してみてくださいね。
最後に五重奏の練習例のPDFを載せておきます。他の曲に応用して使ってください。
この曲が吹きたくなった人は、IMSLPで無料でダウンロードできます。使い方はこちら。
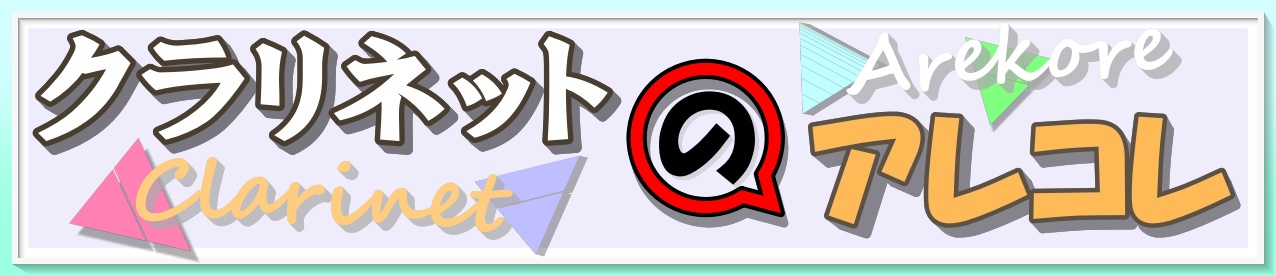


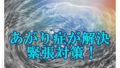
コメント